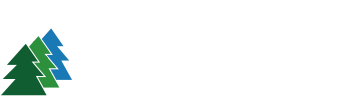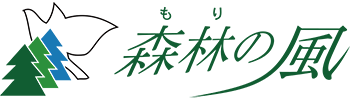こんにちは森林の風事務局です。「県民の森 de 植樹祭」が3月初旬に行われました。
これは県民の森で行われる植樹イベントのことです。県民の森は、全国各地にある森林公園で、緑化推進や自然体験などを目的としています。毎年、公益社団法人三重県緑化推進協会と共同で開催しています。植樹には三重トヨペットから寄贈された苗木が使われます。

三重県緑化推進協会の会長は挨拶の中で「子どもが小さいいうちから緑に親しんでもらうことに意味がある。みんなで緑を増やしカーボンニュートラルにつなげたい」とおしゃられていました。また、三重トヨペットの社長も自社製品のアピールと関連付けて温暖化対策関係について熱弁しておられたような・・


そう言えば、このところCO2吸収量調査のネタばかりを書いていたら
そのことに関心を持っている方からの問い合わせがボチボチあるのだけれど、イヤイヤ当団体は
単なるNPO法人だから・・・研究機関でも専門機関でも無いので難しいことは答えられないし、
出来もしません。ただ、お上のお達し通りにしているだけですから・・


当団体がしていることは、樹種ごとに胸高直径と樹高を測り、それらから地位指数という値を推定します。地位指数とは、木の生育状態を示す指標です。乾材積表という表から、地位指数に対応する成長量を見つけます。乾材積表とは、木の体積や重さを求めるための表です。成長量からCO2吸収量を算出します。この方法では、枝や根、葉などのバイオマスも考慮していますが、CO2吸収量だけでは森林生態系全体の状態は分かりません。森林生態系全体では、土壌中の生物や微生物もCO2を呼吸しています。そのため、森林生態系全体のCO2収支を得るには、土壌呼吸量も測定する必要があります。

森林生態系全体をモニタリングするには、バイオマスだけでなく、土壌中の地中生物や微生物の呼吸も測定しなければなりません。当団体では、そのようなことはできません。しかし、私たちには化学研究所の所長だった会員がいます。彼は私たちが管理しているフィールドの土壌分析を担当してくれていました。彼が使っていた土壌分析器は今もありますが、使われていません。残念なことに、彼は休会中です。彼がいれば、土壌呼吸量も測定できたかもしれませんね。

それに森林のCO2吸収量を評価する方法は問題があります。世界中で同じ基準がありません。そのため、企業や団体は自分たちで算定手法を決めています。例えば、日本では樹木だけでなく土壌呼吸量も考慮していますが、アメリカでは樹木だけを見ています。このように、算定手法が異なると、CO2吸収量の比較や信頼性が低くなりますよね。

日本国温室効果ガスインベントリ報告書にCO2吸収の計算方法は書かれていて、どこの企業も団体もこれを参考にしてはいると思うのだが…というかこれを使用していなければ、どうやって計算すれば良いのやらまったく見当がつかない・・使用してない所は、まさか、適当とか…言ったもの勝ちとかという感じなのか?

きっと森林CO2吸収量の算定・評価方法などといったものは半端な知識の素人にはまったく手が出ないものなのであって私共が考えられる領域でのないと思うので与えられたマニュアル通りに調査している。